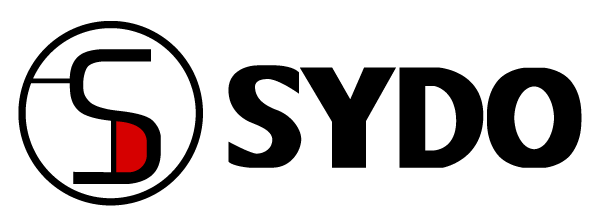1.仇討ちとは
国語辞典で「仇討ち」を調べると、
主君・親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすこと。江戸時代、武士階級で慣習として公認されていたが、明治6年(1873)禁止された。
とあります。書いてある通り、仇討ちとは主君や親を殺された武士が、幕府に仇討ちをしますという届出をして逃げる敵を見つけ出し討ち取ることで、ちなみに敵討ちと仇討ちは同じ意味の言葉です。
日本で行われた仇討ちは、わかっているものだけで370件あります。内容がわかっているものがその数なので、内容のわからないものを入れると膨大な数になるでしょう。
とても有名な仇討ちを挙げると、
寛永11年(1634)、渡辺数馬と荒木又右衛門が河合又五郎を討った伊賀上野の仇討ち(鍵屋の辻の決闘)
寛文12年(1672)、奥平源八ほか多勢が奥平隼人、同大学等を討った市谷浄瑠璃坂の仇討
元禄15年(1702)、大石内蔵助等46人が、吉良上野介を討った本所松坂町の仇討ち(赤穂事件)
等があります。
この三つの仇討ちは講談や芝居、また映画やテレビでも登場する仇討ちですね。
しかし、芝居の中での仇討ちは、仇討ち免状を振りかざし、竹矢来の囲いの中で、太鼓を合図に双方斬り結ぶ。そのいでたちは鎖帷子と白鉢巻。多勢の助太刀がつき、見事討ち取ることが出来ればはなばなしく主の元へ帰る。
実際のところ、仇討ちはこんな形式で行われていたのでしょうか。実際は仇討ちの旅とは、成功率1%の大変な苦労の旅だったのです。
2.仇討免状とは
仇討ちものの芝居などでは、奉書の包紙の上に「仇討赦免状」などと麗々しく書き、切り札として危ないところで取り出す。という展開がありますが、実際にはこのような免状は発行されませんでした。
実際は事前に届け出て登録し、仇討の本懐を遂げても、敵討に間違いないことを証明してくれるだけでした。その証明があれば殺人罪にとわれずその場ですぐ釈放されます。
事前に登録がなければ、牢に入れられて殺人容疑で調べられますが、吟味の結果敵討ちとわかれば釈放されたようなので、登録のご利益は知れたもので、相手を委縮させるような切札にはならなかったようです。
3.仇討ちは竹矢来の中で行われた?
芝居や浮世絵での仇討は、双方白鉢巻に白装束、その下には鎖帷子を着て、竹矢来の囲いの中で勝負をする。殿様も特等席で見ているし、外には見物人がたかる。
というスタイルですが、本当にこのようなスタイルで仇討は行われたのでしょうか?
どうやらこのスタイルで行われた仇討はごくごくまれだったようです。
研究家のこれまでの調べではこのスタイルで行われたとされる仇討は2例あったそうです。
その中の1つは、宝暦12年(1762)5月に佐々木清十郎と中川十内が敵の佐々木九郎右衛門を討った時で、この仇討は奥州中村藩主相馬恕親が竹矢来の中で勝負させました。
その勝負は、二重間に十間の竹矢来を結いまわし、検使として目付、侍頭各3人、徒目付2人、小目付12人、さらに足軽50人が警戒にあたるというものものしさで、敵討の故実として水盃をし、太鼓を合図に斬りむすんだとあります。
暑さが厳しい旧暦の5月末なので、疲れると足軽が双方をひきわけて水を飲ませ、一息入れてからまた戦わせたと、まるでボクシングのラウンドを重ねるようなやり方だったそうです。他の1例もほとんど同じやり方であったとされています。
芝居や浮世絵の仇討は、この例を取り上げて描かれているのですね。
ところで、仇討で鎖帷子なんか身に着けてもいいんでしょうか?
どうやらこれも、芝居や浮世絵ならではで、相馬の仇討では、水盃をする前に、双方着物の下に鎖帷子を着ていないかどうかを検使役があらためました。
こんなスタイルの仇討は、討手が殿様によほど縁があるか、または義侠の殿様にぶつからない限りあり得ないスタイルなので、2例しかないのは当然と言えるでしょう。
あとのすべての仇討は、仇人に逃げられないように不意討をしました。よく名乗りをあげてから討ったとありますが、実際は一太刀あびせてから名乗ったのが多かったそうです。
4.討手の作法
仇討ちにももちろんルールがあり、討ってはならない相手がいます。
例えば、もし父親が殿様の逆鱗に触れ、お手討や上意打ちにされてしまっても、その子が殿様を敵としてねらうことは出来ません。
たとえ殿様がひどい奴であろうと、当時の道徳としては主君を恨めませんでした。
また、本人同士が申し合わせて、力をつくして果し合いをした場合、負けたからといってその子や弟が相手を敵と呼ぶのは許されません。戦場の一騎打ちもそうですが、お互いに覚悟をして臨んだことであり、怨むすじあいはないということです。
敵討は「不倶戴天」の怨みが根本にあり、その怨みの正当でないものは認められませんでした。
ところで、誰が誰の敵を討つのか。これにもルールがあります。
それは尊属(目上の者)の敵は卑属(目下の者)が討つというものです。
つまりは、父の敵を子が討ち、兄の敵は弟が討ち、叔父の敵は甥が討つというように殺された人の目下の親族が討手となります。その逆は基本的に認められませんでした。
目下の者の敵を目上の者が討つことは認められないので、妻が殺されてしまってもその敵を夫が討つことは認められません。
叔父よりも遠い縁者の場合は助太刀に回ります。
主君が殺された場合でも、子や弟がいればその人達が出ます。師匠の場合でも同じく子や弟が先で、弟子は助太刀に回ります。その師匠に近い肉親がいない場合にはじめて弟子や家来がやることになります。
5.助太刀の作法
江戸時代の初めには、武士が家名を重んじて一族の結束が固かったため、敵討になるとひどく遠縁の者まで助太刀に出ました。
討手に助太刀がつけば、負けずに仇人の方にも助太刀がつき、浄瑠璃坂の仇討には、助太刀が集まって、討手側が40人、仇人側が60人という大規模な仇討となりました。
助太刀はあくまで助っ人なので、討手が危なくならなければ手を下すことはしません。
討手にとっても、助太刀の手をかりて討つのは不名誉とされたので、助太刀の手をかりずに仇人を討つことが心得でした。荒木又右衛門の助太刀ぶりがその模範とされています。
この助太刀といえども、主人がいれば願い出て暇をもらう(辞職する)必要がありました。
また奉行所に届け出て御帳につけてもらうことも討手と同様でした。
6.仇討の成功率は1パーセント
仇人が討たれないようにしゃにむに逃げるのを江戸時代の電車も電話も写真もない時代に追うのは現代から考えると気が遠くなるほどに大変なことです。
そのため仇討の討手が鬢付け油売りや膏薬売り小間物屋に化けて敵を探ったという記録があり、討手も策をこらしているのがわかります。忠臣蔵でも立派な武士が、米屋や笹竹売りに化けています。
江戸初期には武士道が鼓吹され、諸大名もその軌範として討手の保護をしました。出発する討手に刀や金を与え、留守中にはその家族を扶養しました。めでたく敵を討ち果たした場合にはもちろん褒賞がありました。
しかし享保(1716~35)以後になると、武士道が形骸化したことと、原因も闇討や喧嘩が多くなったので、待遇がすっかり変わってきました。
仇討の手続きをすると、辞職しなければならなくなりました。敵討は私事で、公務を差し置いて私事をするのだから、辞職するのは当然という価値観になっていたのです。
見事敵を討つことが出来ても、必ずしも職に戻れるわけではありませんでした。あざやかな討ちっぷりならまだ望みはありますが、みっともない討ちっぷりだと復帰は難しくなります。
仇人を探すのがまず大変なのに、見事な討ちっぷりを求められるわけです。
金銭面も大変です。
はじめは親戚知人から経済援助を受けるも、仇討の旅が長引くとそれは絶え、討手本人は旅先で、家族は本国で乞食同然となってしまう。武士としての体面上討手は国に帰ることは出来ず、結局は一家離散におちいってしまう。仇討は哀しく悲惨なものなのです。
だからといって不俱戴天の仇はそのままにするわけにはいかなかったのです。
いかがだったでしょうか!
今回は仇討の作法に迫りました。
仇討の物語は時代劇でもよく描かれますが、その中では当然ながらフィクションも多く、実際は成功率1%の大変な旅だったのですね。
時代における武士道のあり方の違いで仇討の待遇がここまで違うとは…。
助っ人で大活躍をした荒木又右衛門などは一気にその名を知らしめましたが、その時代はまだ武士道が形骸化する前ですし、そんな例はすべての仇討の中でも稀有なのでしょう。
【参考文献】
江戸考証読本 著者:稲垣史生